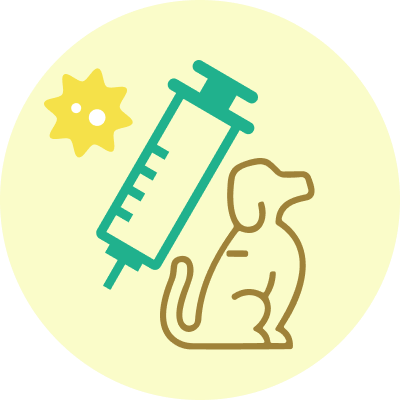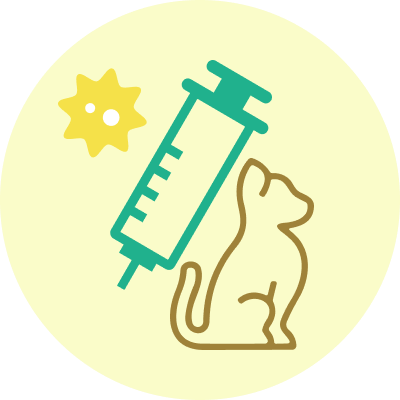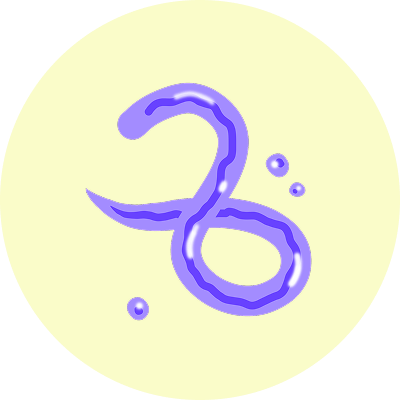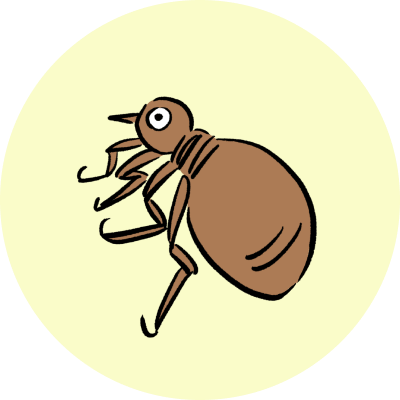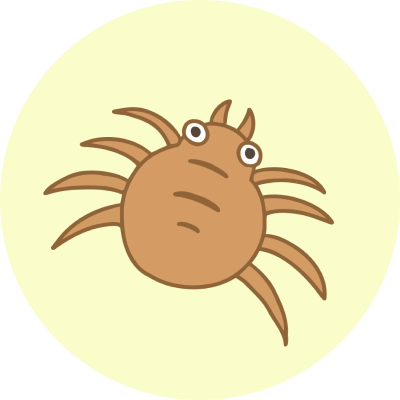診療科目
お気軽にご連絡ください
042-771-1112各種予防(ワクチン、フィラリア、ノミ、ダニ)
犬のワクチン
混合ワクチンとは
混合ワクチンで予防できる病気は伝染力が強い、致死率が高い病気が多く含まれ、予防がとても大事です。
取り扱っているワクチンと予防できる病気
6種と10種類のワクチンが接種可能です。
| 混合ワクチン成分 | 6種 | 10種 |
|---|---|---|
| 犬ジステンバー | ● | ● |
| 犬パルボウイルス感染症 | ● | ● |
| 犬伝染性肝炎 | ● | ● |
| 犬アデノウイルス感染症 | ● | ● |
| 犬パラインフルエンザ感染症 | ● | ● |
| 犬コロナウイルス感染症 | ● | ● |
| 犬レプトスピラ感染症(カニコーラ) | - | ● |
| 犬レプトスピラ感染症(イクテロヘモラジー) | - | ● |
| 犬レプトスピラ感染症(グリッポチフォーサ) | - | ● |
| 犬レプトスピラ感染症(ポモナ株) | - | ● |
接種する期間や時期
| 1歳 未満 |
6週齢以降から接種可能、最終接種が16週齢以降になるようにその後1~2回追加接種 |
|---|---|
| 2歳 | 前回の混合ワクチン接種から1年後に接種(免疫の底上げが期待できる ブースター効果) |
| 3歳 以降 |
前回の混合ワクチン接種から1年後に接種 |
*3歳以降の場合は犬ジステンパー、犬パルボウイルス、犬アデノウィルスに関しては抗体価測定(ワクチンの免疫効果が十分残っているかの確認ができます)も可能です。
狂犬病予防ワクチンとは
狂犬病は人間も含め哺乳類がかかる伝染病で、発症するとほぼ100%死亡してしまう恐ろしい病気です。狂犬病ウイルスに感染した動物にかまれることで感染します。日本での発生は現在認められていませんが、海外から狂犬病ウイルスが侵入する可能性は拭えません。
日本では、流行を防ぐため飼い犬の登録及び毎年の予防注射が、狂犬病予防法により義務付けられています。当院では、一年を通して、狂犬病の予防接種が可能です。
*当院では相模原市、町田市への代行手続きが可能です。その他の地域ではワクチン接種証明書を発行いたします。
接種する期間や時期
生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に1回目を接種し、その後は毎年1回、4月~6月の間に接種します。
猫のワクチン
混合ワクチンとは
混合ワクチンで予防できる病気は伝染力が強い、致死率が高い病気が多く含まれ、予防がとても大事です。
取り扱っているワクチンと予防できる病気
3種と5種のワクチン接種が可能です。
| 混合ワクチン成分 | 3種 | 5種 |
|---|---|---|
| 猫汎白血球減少症 | ● | ● |
| 猫ウイルス性鼻気管炎 | ● | ● |
| 猫カリシウイルス感染症 | ● | ● |
| 猫白血病ウイルス感染症 | - | ● |
| 猫クラミジア感染症 | - | ● |
接種する期間や時期
| 1歳 未満 |
9週齢以降から接種可能、最終接種が16週齢以降になるようにその後1~2回追加接種 |
|---|---|
| 2歳 | 前回の混合ワクチン接種から1年後に接種(免疫の底上げが期待できる ブースター効果) |
| 3歳 以降 |
前回の混合ワクチン接種から1年後に接種 |
*3歳以降の場合は猫パルボウイルスに関しては抗体価測定(ワクチンの免疫効果が十分残っているかの確認ができます)も可能です。
抗体価検査とは
抗体価検査とは、血液中の抗体価を測定して、感染症に対する発症防御能を評価する検査です。少量の血液を採取して行うことができ、ワクチンを接種することで得られる免疫力の一部を調べることで現在の免疫力を知ることができます。
抗体価検査の結果により抗体価が一定以上ある場合は免疫力が維持されているため、追加のワクチン接種は不要と判断できます。また、抗体価が低い場合は接種が必要になります。
*海外のガイドラインで3年に1度のワクチン接種の報告も出ていますが、日本国内での使用ワクチン、犬種、猫種での報告ではないため、当院では接種の必要性を抗体価で判断しています。実際に数年抗体価が維持できている場合も有れば、1年後には抗体価が低下している場合も有ります。
抗体価検査のメリット
- ・ワクチンを理想的な間隔で接種可能
- ・外出やほかの犬との接触について判断できる(ホテル、ドックラン等で証明書が必要な場合も有ります)
抗体価検査のデメリット
- ・特定の病気の抗体しか調べられない
- ・結果が出るまでに犬1~2日、猫1~2週間必要になる
- ・抗体が不十分だった場合ワクチン接種が必要になる
抗体価検査を受ける期間や時期
通常はワクチン接種予定日前後に測定します。
*個々にあったワクチン接種相談も可能ですのでお申し付けください。
フィラリア予防
フィラリアとは
蚊により媒介された犬フィラリアという寄生虫が心臓などに寄生し様々な症状(咳、お腹に水がたまる、食欲不振など)を起こす感染症です。
予防期間は蚊が出始めてから1か月後から蚊が見られなくなってから1か月後までです。
毎月1回の投薬または年1回の注射で予防します。
わんちゃんの病気と思われがちですが、ねこちゃんも予防が大切です。
フィラリア予防について
犬
予防薬の種類は、内服薬(錠剤タイプ、おやつタイプ)、スポットタイプ(塗布薬)、注射薬があります。
-
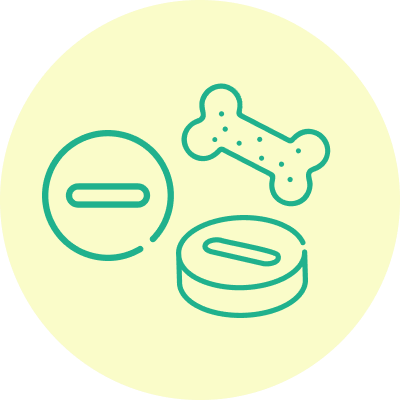
内服薬(錠剤、おやつタイプ) -
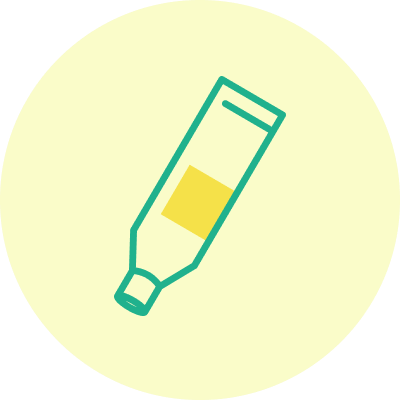
スポットタイプ(塗布薬) -
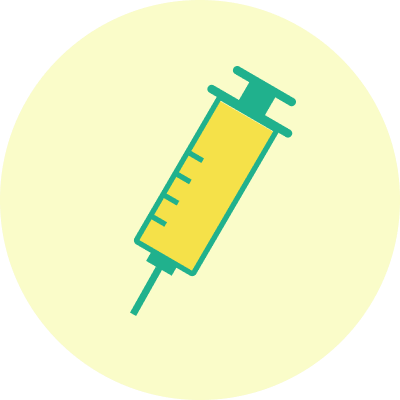
注射薬
猫
スポットタイプのみご用意しています。
-
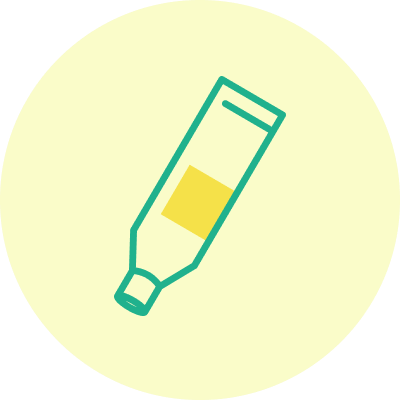
スポットタイプ
フィラリア検査の説明
犬のフィラリア症の検査には、主に次の2つの方法があります。
・抗原検査…検査キットを使って血液中のフィラリア成虫の抗原を確認する検査
・ミクロフィラリア検査…血液中のフィラリアの幼虫(ミクロフィラリア)を顕微鏡で確認する検査
年に1回(主に3〜5月)、上記の検査で陰性であれば予防薬を処方いたします。
ノミマダニ予防
ノミ予防とは
ノミは体長1~3㎜ほどで皮膚に寄生し、かゆみやアレルギー反応を引き起こすだけでなく、重篤な病気を引き起こすこともあります。適切な予防策を講じることで、ノミからペットを守ることができます。以下の様な病気を引き起こすことがあります。
| アレルギー性皮膚炎 | ノミの唾液に対してアレルギーを引き起こし、激しいかゆみや炎症を伴う皮膚疾患が発生します。 |
|---|---|
| 感染症の媒介 | ノミがバルトネラ菌を媒介することで猫から猫へこの菌が伝染します。猫は通常症状が出ませんが、人が感染するとリンパ節の腫れや発熱などの症状が出ることがあります(猫ひっかき病)。 |
| 貧血 | 大量のノミが寄生することで、動物の血液を吸い続け、深刻な貧血を引き起こすことがあります。 |
ノミ予防について
犬
内服薬(錠剤タイプ、おやつタイプ)、スポットタイプ(塗布薬)を用意しています。
-
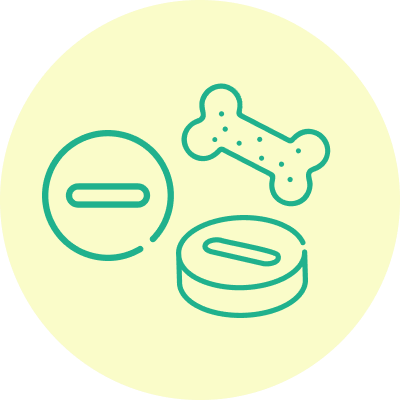
内服薬(錠剤、おやつタイプ) -
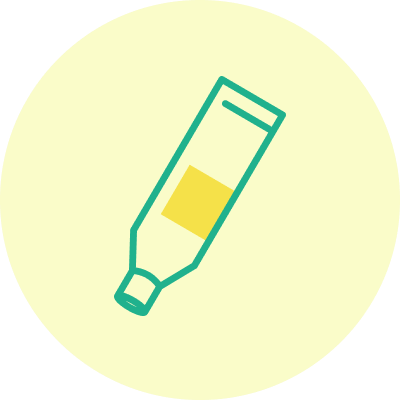
スポットタイプ(塗布薬)
猫
スポットタイプをご用意しています。
-
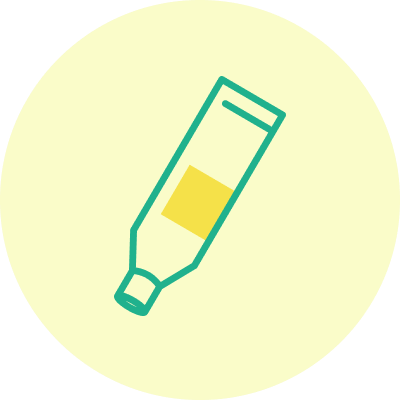
スポットタイプ
ノミ予防についての詳細や予防薬の処方をご希望の方は、ぜひ当院までご相談ください。わんちゃん、ねこちゃんの健康を守るために、専門的なアドバイスと最適なケアを提供いたします。
マダニ予防とは
マダニは体長3~8mm(吸血前)で吸血すると10~20mmほどで、草むらや森林、公園などに生息しており、動物に付着します。皮膚炎や感染症の原因となり、場合によっては命に関わることもあります。適切な予防策を講じることで、マダニからわんちゃん、ねこちゃんを守ることができます。
マダニが媒介する感染症
- バベシア症・ヘモプラズマ症
- マダニを介して赤血球に感染する病気で、重度の貧血や黄疸、発熱を引き起こす病気です。
- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
- ウイルスによる感染症で、主に発熱、嘔吐、下痢、血小板や白血球の減少を伴います。重篤な症状に進行しやすく、現在のところ効果的な治療法が確立されていないため、予防が非常に重要です。人にも感染する疾患です。
当院のノミ・マダニ予防
犬
内服薬(錠剤タイプ、おやつタイプ)、スポットタイプ(塗布薬)を用意しています。
-
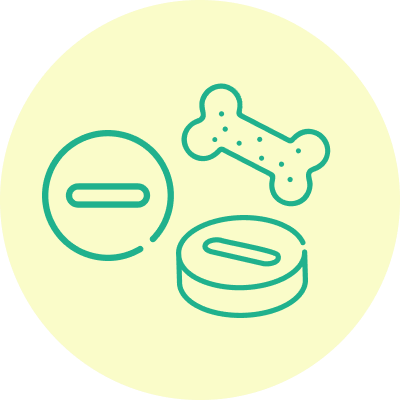
内服薬(錠剤、おやつタイプ) -
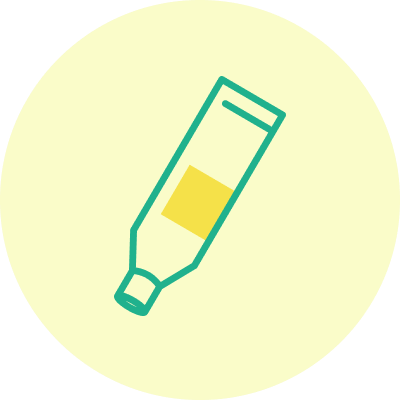
スポットタイプ(塗布薬)
猫
スポットタイプのみご用意しています。
-
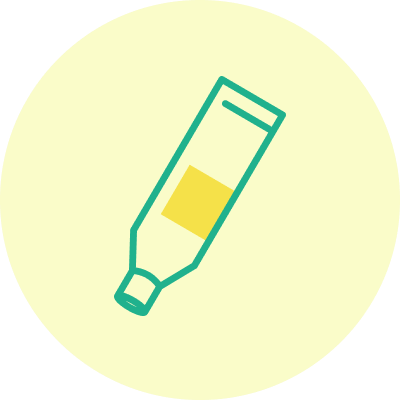
スポットタイプ
ノミ予防についての詳細や予防薬の処方をご希望の方は、ぜひ当院までご相談ください。わんちゃん、ねこちゃんの健康を守るために、専門的なアドバイスと最適なケアを提供いたします。